令和2年10月5日 6年生による地域調べ学習の報告





その発表を朝会で全校の皆さんに報告してもらいます。 【上野の地形と歴史について】 こんにちは。ぼくたちは、忍岡小学校の六年生です。ぼくたちが上野について調べたことを発表します。聞いてください。 みなさんは、上野の地形について調べたことがありますか?上野は、台地と下町の境目に位置しています。台東区はほとんど坂がありませんが、上野公園に上る所は、登坂です。丁度、パンダ橋から下は、昔、海だったそうです。私たちの忍岡小学校がある辺りは、この上野台地と東大のある本郷台地に挟まれて丁度谷になっている所です。 上野公園の中には、五世紀ごろのものと言われる摺鉢山古墳が今でも残っています。当時は、今の国立博物館や西洋美術館の辺りにも古墳があったそうです。私たちの忍岡小学校近くのマンションを立て直した時に遺跡も出てきていて、上野の辺りには、昔から人が住んでいたことがわかります。忍岡小学校の前の不忍通りは昔「しのぶ川」という川でした。江戸時代には、そこに三っつの橋(将軍様用、お坊さん用、庶民用)がかかっていたそうです。その名残が上野で有名なあんみつ屋さん「みはし」という名前に残っています。清水観音堂のふもとに湧き水が出ていて「しのぶ川」という石碑も建てられています。 上野は、昔は立派な上野山でした。そこが江戸時代寛永寺の土地となり、発展しました。しかし、上野戦争で焼野原になりました。その後地に病院を建てようとした政府に対し、オランダの医師ボードワン博士が「元はきれいだった場所に病院を建てるのは、もったいない」と反対し、今の上野公園ができたそうです。その後、アメリカ大統領だったグラント将軍が何種類ものはなや桜を植えたり、いろいろな人たちが上野の自然を守ろうとしたりした結果、今のように春のお花見をはじめとして、四季を楽しめる上野公園ができあがりました。 【上野の自然について】 次に上野の自然について発表します。上野には、多くの種類の植物があり、どの季節でもいろいろ見て楽しめます。 まず、春、三月から五月の間では、サクラ、ウメ、サザンカ、ツバキ、カンザクラ、コブシ、春ボタンが見られます。夏、六月から八月の間では、ハナミズキ、アジサイ、ハングショウ、アメリカンデイゴ、ハスが見ごろです。秋、九月から十一月の間は、ヒガンバナ、ユリノキ、ハゼノキ、イチョウ、モミジが見られます。冬、十二月から二月の間は、カンザクラ、ウメ、サザンカ、スイセン、ボタンが見られます。上野公園にある植物は、手入れをしてくださるか方々のおかげです。 ところで、上野の桜は三代将軍徳川家光の頃、奈良の都の周りと同じように上野の山を桜できれいにしようと、天海僧正(てんかいしょうじょう)が吉野の桜を植えたのがはじまりと言われています。現在、上野公園には、五十種類以上の桜の種類があり、八百本もの桜の木があります。今年は、中止になりましたが、毎年、三月の終りから四月にかけてお花見客でにぎわいます。不忍池の周りは、六月ごろアジサイがとてもきれいです。五月から六月にかけては、ハスの葉の緑で池がうめつくされます。七月、八月はとてもきれいなピンクの花が咲きます。九月になると花はまだ咲いていますが葉が茶色になってきます。 三代将軍の家光が徳川家康公をまつるために建てた上野東照宮では、ボタン祭りがあり、多くの人が訪れています。 ぼくは、このように都会でありながら自然の多い上野が大好きです。 令和2年9月7日「上野の重要文化財」





さて、上野には、寛永寺の五重塔をはじめとしてこの前、6年生と一緒に行った上野東照宮など重要文化財が多くあります。清水観音堂や藝大の旧奏楽堂、科科学博物館の古い建物、国立博物館など明治時代から残っている沢山の文化財があります。そのような所へ学校から歩いて行けるというのはとても恵まれた環境にあるということです。ぜひ、皆さんも時間があったら歩いて訪れてみましょう。 そして、なんと言っても東京で唯一の世界文化遺産、西洋美術館もあります。 今は、人数制限をしていますが、中に入ることもできます。 沢山の美術作品を見ることができます。 今日は、計画委員会から12月の音楽会のキーワード募集があります。 よく聞いてくださいね。 令和2年8月31日「工夫を凝らした自由研究」





暑い日が続くので水分をこまめにとるようにしましょう。 令和2年8月24日(月)2学期始業式





今年は、いつもと違って短い夏休みでした。あまり旅行などにもいけず、自宅や周辺で過ごすことが多かったと思いますが、新しい発見もあったのではないでしょうか。 さて、忍岡小学校では、毎年百人一首の暗唱を行っています。コロナ禍で実際にやることが難しいかもしれませんが、ぜひ、今から800年前ぐらいの日本人が詠んだ歌を覚えてください。今の時代のようにパソコンや車はありません。でも季節の移り変わり、人の心の思いは今に通じるものがあります。その当時の暦は太陰暦でしたので今と少し季節が違います。7月、8月、9月は秋になります。毎日暑くて秋とはほど遠い感じですが、田んぼは黄色一色、稲刈りの季節となっています。 「秋の田の かりほの庵の とまをあらみ わが衣手は 露にぬれつつ(天智天皇)」 という歌があります。この歌は、百人一首の中でただ一つ、農民の姿を詠んだものです。 収穫の秋の田んぼのわびしく静かな風情が伝わってきます。百人一首の一番最初に出てくる歌なのでまずこの歌から覚える人も多いのではないでしょうか。 長い2学期健康に気をつけてぜひ百人一首やいろいろな本なども読んでください。 令和2年7月31日(金)1学期終業式「その炎は消えていない」



分散登校、マスクをつけての日常生活、限られた活動、静かな給食、手洗い・うがいの徹底 いろいろな制約がありましたがみなさん、本当によくがんばって健康に過ごすことができました。今年の夏休みは3週間という短いものです。いつもの年のように旅行に出かけたりできないと思いますが、違った楽しみをみつけてください。 本当なら今、東京オリンピックでこの東京はにぎわっているはずでした。 一週間前の開会式の日に競泳の池江里璃花えい子選手がプレゼンテーターを務める「TOKYO2020+1」の動画は配信されました。競泳の日本代表選手が忍岡小学校には毎年訪れ、オリンピックへの意気込みを話してくれました。一緒にプールで泳いでもくれました。彼らも今どのような気持ちで過ごしているのでしょうか。 来年、オリンピックがどうなるか、それはわかりません。でもこの動画の最後に聖火をもった池江選手と「その炎はまだ消えていない」というメッセージが流れます。 来年の今頃、コロナウイルスの感染拡大が収まり、もとのような日常が訪れることを願ってやみません。 私たちもあきらめずに少しずつの努力を絶やさずがんばりましょう。 「お薦めの一冊」

『こいぬのルナ、コロナウイルスにたちむかう』という本です。 アメリカの作家が「COVID-19]と今世界で起こっていることを子供たちが知る助けになればと思って書いた絵本です。 わかりやすい文言の解説もあるので機会があったら読んでみてください。 令和2年7月27日「夏休みに書いてみよう!行ってみよう!」

遠くに出かけられなくても都内でも面白い所があります。実は、先週の土曜日に校長先生は仕事の関係で「虹の下水道館」へ行ってきました。皆さん、マンホールカードって知っていますか?道端にある東京都のマンホールの蓋tは、都の花「桜」都の木「いちょう」そしてユリカモメをイメージしたイラストになっています。今度道路を歩いたらよく見てみましょう。下水道管に行くと地面の下がどのようになっているかがわかります。また、都内のマンホールの様子もわかります。有明にあるのですが、有明には他にも見る場所がいろいろあります。今年の夏の過ごし方、ちょっと工夫して楽しく過ごしてください。 令和2年7月20日 「コロナ禍広がる善意の輪」





令和2年7月13日「台東区歴史・文化検定」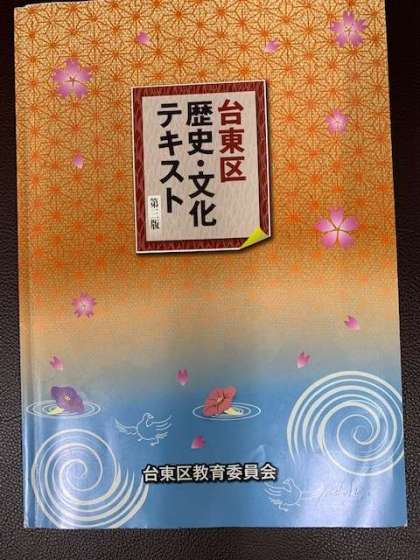



令和2年7月6日 「もぐもぐポストから」





ずっとなかった給食が6月半ばから始まりました。最初はカレーライスでした。まだ品数は三品ですが、栄養士の先生が工夫を凝らしておいしい給食を作ってくれています。給食を食べての感想を書いて入れる「もぐもぐポスト」に沢山のよい感想があったのでみなさんに伝えたいと思います。「大好きなカレーでした。サラダもずっと食べていなかったし、久しぶりの牛乳でおいしかったです。」「しゃべりながら食べることはできず、いつもと違う給食だけれどもこれからも静かにがんばります。」「久しぶりの給食おいしくて、とても嬉しかった。これからも楽しみにしています。」「おいしい給食をありがとうございます。ぼくは、グラタンが好きなので今日のメニューにあってラッキーです。」 これからも給食を楽しく食べましょう!! 令和2年6月29日「隅田川今・昔」



今は、沢山の橋がかかっています。5,6年生の中には駅伝大会やわんぱくトライアスロンに参加した人もいると思います。競技をしたリバーサイドスポーツセンターのすぐそばに桜橋があります。それから言問橋、吾妻橋、駒形橋、厩橋、蔵前橋と台東区と墨田区を結ぶ橋があります。さらに沢山の橋が東京湾に続くまでかかっています。レインボーブリッジが見えてくると川は東京湾につながります。 いろいろな時代を見てきた隅田川。 5,6年生は、『台東区歴史・文化検定』を受けます。台東区の歴史の中にも隅田川はいろいろ出てきます。ぜひ、本を読んで勉強してください。 令和2年6月22日「夏至と部分日食」



昨日は、夏至でした。1年で昼間が一番長い日です。これから少しずつ日がみじかくなって年末の12月下旬に今度は日が一番短い日冬至を迎えます。これは太陽の高さによるものです。 また昨日は、日本全国で部分日食が見られました。日食とは、太陽が月によって覆われ、太陽が欠けて見えたりする現象です。地球と太陽の間の直線状に丁度月が入ってくる現象です。沖縄などでは、きれいに見えたようですが、東京はその時間くもりでした。校長先生もがんばって隅田川沿いで見ていたのですが、よく見えませんでした。 けれどよい発見もしました。今まで運行されていなかった水上バスが隅田川を走っていました。少しずつ世の中が動き出したなと思いました。早くコロナウイルスが収束して普通の日常が来ることを願っています。 令和2年6月15,16日「上野動物園ニュース」

さて、みなさんが七夕の時に願い事を短冊に書いて飾る笹ですが、毎年、上野動物園からもらっています。校長先生もこの前、他の先生方と一緒に上野動物園に行って知ったのですが、その笹は園内のいろいろな所から動物園の人が考えて忍岡小学校のみんなのために切り出してくれているものです。大切に使いたいと思います。その笹を見に行くので動物園に行って久しぶりに元気な象やハシビロコウに会ってきました。ゴリラの家族は、先生たちが行くとそばに寄って来てくれました。ペンギンたちは暑いので日があたらない所にこもっていました。ハシビロコウは動いていましたが、先生たちに気付くとピタッと動かなくなりました。早く動物園へ皆で出かけたいですね。もう少し待ってくださいね。大きくなったシャンシャンにも会いたいですね。 令和2年6月8、9日「みんなの作品から教えられたこと」

学校が休みの間、図工の作品を家庭で作ってくたお友達がいます。校内に飾ってあるのでぜひ見てください。どれも工夫されていて素晴らしいです。みなさんの作品から、お家にある材料を使って、イメージを膨らませて工夫して作るとこんなにも素敵な作品ができあがることを学びました。外で出かけられなくて大変だったと思いますが、その中でよくがんばったなぁと、みなさんの作品から元気をもらいました。このような状況下でできないことが沢山あります。でもできることをやれることを見つけて挑戦していくこと、それはきっと大きな力になります。図工の伊野先生の発案で「アマビエ」の絵も飾ってあります。コロナの終息を願いながら校長先生も「アマビエ」の絵を描きました。みなさんからはどんな絵ができあがるか楽しみです。 令和2年6月1日、2日 始業式





皆さん おはようございます。 ようやく学校が始まりました。長い間、おうちでがんばりましたね。 先生たちは、皆さんに会えるのをとても楽しみにしていました。 1年生の皆さん、ようこそ忍岡小学校へ。このような始まりになりましたが、これから毎日少しずつ学校に慣れていきましょう。 新型コロナウイルスは、誰にとっても初めての経験でした。まだなくなったわけではないのでマスク着用、手洗い、うがいに気を付けていかなくてはいけません。 ここに一冊の本があります。少し前まで多くの感染者を出したイタリア。そのイタリアの高校の校長先生のメッセージで、世界中で話題になりました。「これからの時代を生きる君たちへ」というメッセージです。 突然の休校となったイタリアの高校生に送ったメッセージです。ここには、コロナウイルスの感染拡大の中で一番危険なことは、暮らしや人と人との関係など私たちの貴重な財産である人間性がダメになってしまうことだと書かれています。デマに惑わされたり、不安になったり同じ人間同士なのに、傷つけあってはいけません。私たちが互いに喧嘩などしたら、ウイルスが人間に勝つことになってしまいます。医学や科学の進歩を信じて、冷静に動きましょう。と言うような内容です。 いつまで自粛が続くのか、また第2波が来ると言われていて、先が見えず、私たちはとても不安になってしまうことは事実です。でもだからといって、他の国々のことを悪く言ったり、わがままを言って喧嘩をしたりしても何も生まれません。今、何がやれるのだろう、何ができるのだろう、そう考えて一歩ずつ歩んで行くことが大切です。 本の最後には、日本での読者の皆さんにということでこの作者からの後書きが書かれています。「今回の非常事態宣言は、21世紀に生きる私たちが抱いていた確信を揺るがしました。人類は、自分たちが一番強いと思っていたのですが、実は弱いことに気付かせてくれました。スピード社会の中で立ち止まらざる得なくなり、命や愛、友情など本当に大切なものは何か、理解する機会を与えてくれました。」この経験は、わたしたちにとってかけがえのないものになると思います。 学校が始まっても我慢してもらわなくてはいけないこともあります。なかなか以前のように戻れないかもしれません。でもあきらめることなく、この本に書かれているように大切なことは何か考えながら、一緒にがんばっていきましょう。 令和2年6月1日、2日 入学式





なかなか学校に来るこができなくて大変でしたね。今、元気にこの体育館に入ってくるみなさんの姿を見て、さすが忍岡小学校の一年生だと思いました。制服がとてもよく似合っていますね。 さて、この袋の中には、何が入っているでしょう?じゃーん、パンダさんです。忍岡小学校は上野動物園に一番近い小学校です。パンダの森も新しくなって早く動物園に行きたいのですが、残念ながらまだ入れません。でもできるだけ早くにいろんな動物に会いにいきたいと思います。「パンダさん、小学校で大事なことってなあに?」そうですね、「あいさつ」です。「おはようございます」、「こんにちは」、残念ながらマスクをつけているのであまり大きな声は出せませんが、先生やお友達とあった時は、きちんと挨拶するようにしましょう。 あれ、まだ何か袋の中にいますね、あっハシビロコウです。上野動物園の西園に入るとすぐの所にいます。ハシビロコウは鳥の仲間ですがあまり動かない鳥で有名です。とても可愛らしい目をしていて、じっと見ているとだんだんちょっと動く様子がわかります。周りの様子をよく見ているのですね。ハシビロコウも一生懸命生きています。みなさんも周りの様子をしっかり見て、とくに先生のお話をよく聞いてください。コロナウイルスの感染拡大予防のため、まだなかなか思うような生活を送ることができません。でも一日一日を大切に歩んでいきましょう。 一年生のみなさん、「あいさつをしっかり言う」「先生のお話をよく聞く」この二つのことをぜひ心がけてください。コロナウイルスの収束がみられたら、みなさんのお父さんやお母さんも呼んで一緒にもう一度入学式を行う予定です。その時、また聞きますのでぜひ、挨拶とお話を聞くことをこころがけて毎日がんばってください。元気に明後日また来てくださいね。 これで校長先生の話を終わります。 令和2年5月25日「世界はつながる」

令和2年5月18日「台東区の祭り」





なんでしょう?そう、祭囃子の音です。下谷神社から始まり、毎週のようにどこかでお祭りがあるのが台東区です。三社、鳥越神社など大きな祭りの他、小さな神社でもお祭りが続きます。この池之端の地域は、8月の終りに諏訪神社のお祭りに合わせて四丁目のお祭りがあり、9月には七倉稲荷神社のお祭りがあります。去年は沢山の子供たちが参加してくれました。今年はそのすべてのお祭りが中止や延期になってしまい、御神輿が大好きな校長先生はとても寂しいです。ですから、今、祭りの手ぬぐいでマスクを作ってお祭り気分を楽しんでいます。 5年生以上のみなさんは、『台東区歴史・文化検定』という冊子が手元にあると思います。そこには、台東区の行事や歴史が沢山、書かれているので、ぜひ読んでみてください。そして、自由に外出できるようになったらいろいろと訪ねてみてください。 令和2年5月11日「145周年を迎えて」

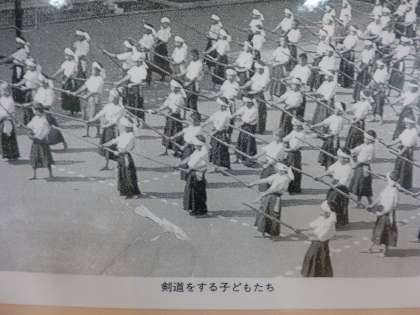



|
|