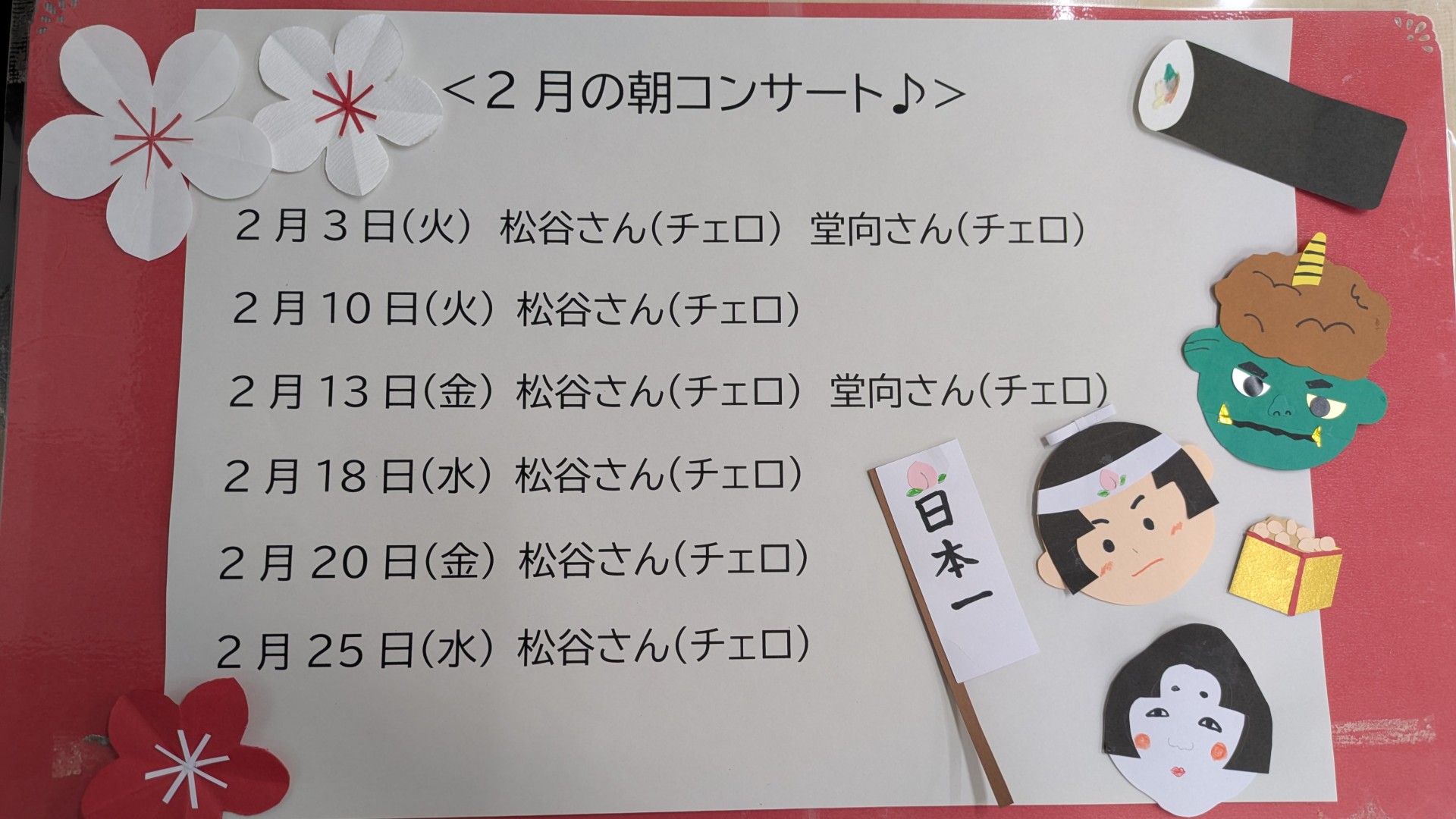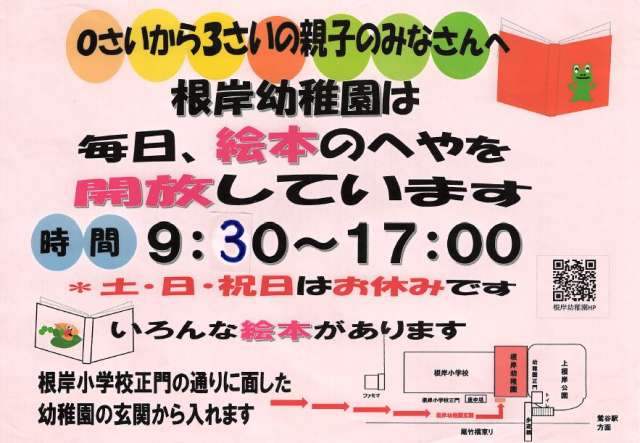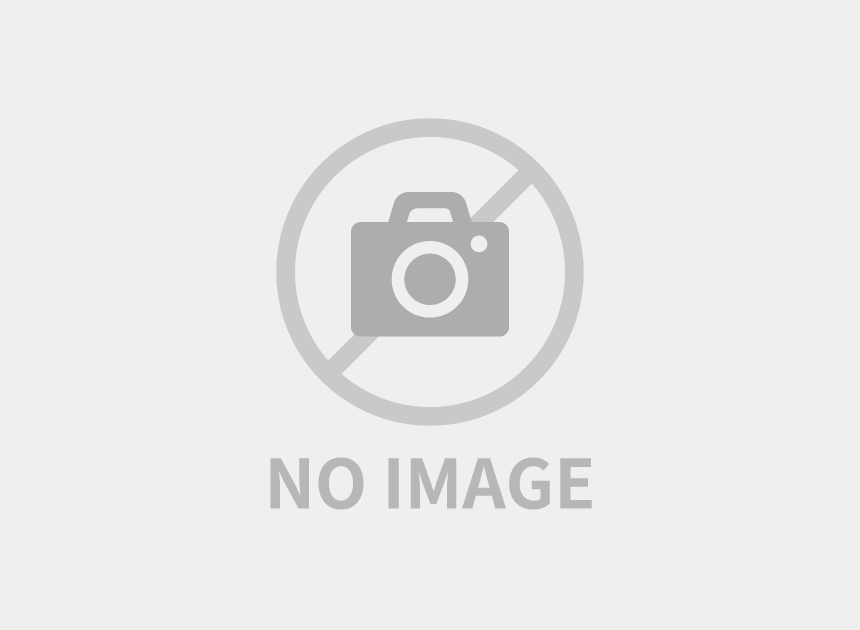来訪者の方へ
台東区立根岸幼稚園のホームページへようこそ!
朝コンサートやってます♪
未就園児親子の方、地域の方、どなたでもいらしてくださいね🎵
未就園児の会のお知らせ
⭐︎今年度の入園説明会は終わりましたが、来園やお電話での問い合わせにも対応しています
⭐︎次回のいちごの会は2月12日(木)は来年度入園決定された方のみの参加となります。
⭐︎次回のいちごみるくの会は2月24日(火)10時からです⭐︎
未就園児の会は申し込み不要です
園選びでお悩みの方、どんなことでもご質問ください
お待ちしています
新着記事
新着配布文書
-
出席届(感染性胃腸炎) PDF
- 公開日
- 2025/11/17
- 更新日
- 2025/11/17
-
出席届(インフルエンザ) PDF
- 公開日
- 2025/11/17
- 更新日
- 2025/11/17