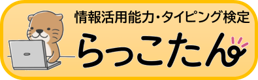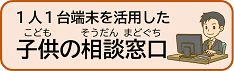新着記事
-
大森第五小学校の児童が育てたサナギをいただいて玄関で観察しているところですが、先日、ナミアゲハが全部羽化したため、今度はアオスジアゲハのサナギをいただいてきました。一頭だけナミアゲハのサナギが混じって...
2025/06/27
お知らせ
-
6月9日(月)の5・6校時に体育館で水道キャラバンの方にお越しいただき、水についての学習を行いました。初めに、映像を交えながら水源林やダムのはたらき、水道局で働く人々の思いや苦労を学んだり、グループで...
2025/06/10
できごと
-
大森第五小学校の子供たちが育てたナミアゲハのサナギから、成虫がどんどん羽化しています。1枚めの写真のように、緑色のサナギが透けてきて、成虫の羽が見えてくるようになると羽化が近いです。2~4枚めの写真は...
2025/06/09
できごと
-
昨年度、創立120周年記念特別授業がきっかけとなり、今年度から正式に教育課程に位置付けた学習です。6月4日(水)高橋総本店調理道具部での弟子入りの様子をお知ら...
2025/06/06
できごと
-
本日、3年生は区内巡りの校外学習に行ってきました。午前中は、2つの班に分かれて浅草文化観光センターと隅田川沿いを散策しました。文化観光センターでは、8階まで180段を超える階段をのぼりました。のぼった...
2025/06/06
できごと